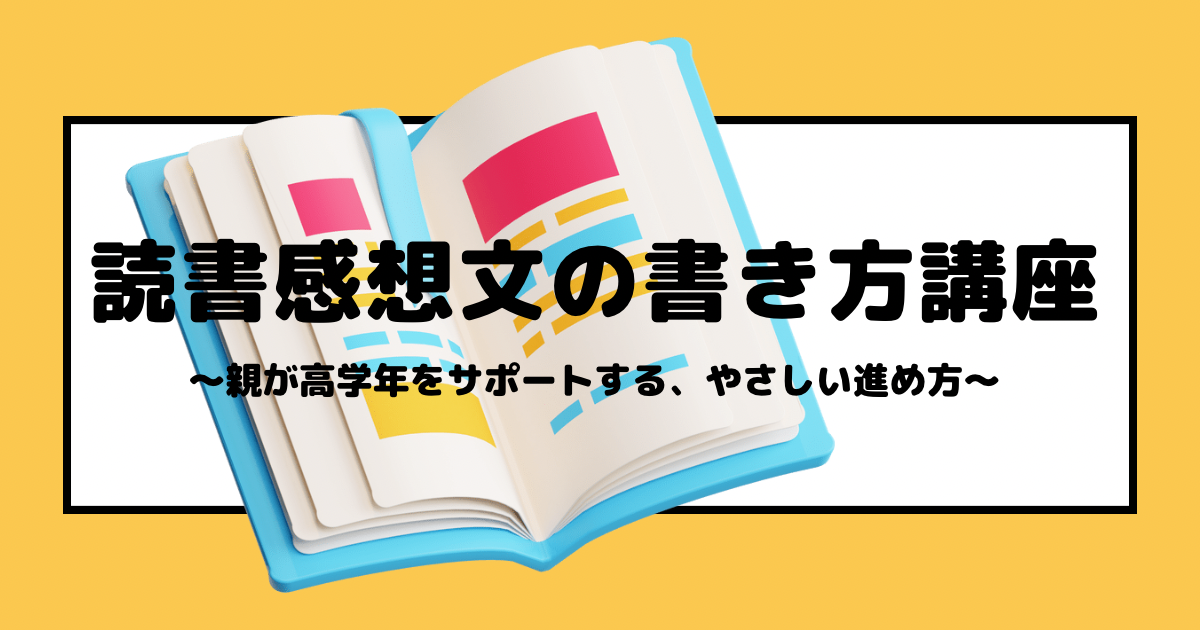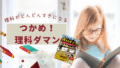読書感想文。
それは、子どもが本を通して感じたこと、考えたことを「自分の言葉」で表す、大切な表現の練習です。
でも、いざ書こうとすると…
- 「何を書けばいいのかわからない」
- 「あらすじばかりになってしまう」
- 「書き始めるまでに時間がかかる」
そんな声が、子どもたちからよく聞こえてきます。
この記事では、小学5〜6年生の保護者の方に向けて、
読書感想文を「親子で楽しく、自然に進めるためのコツ」を、やさしくお伝えします。
1. 感想文は「心の動き」を言葉にするもの
まず大切なのは、「読書感想文=あらすじを書くもの」ではないということ。
感想文の本質は、「心が動いた瞬間」を言葉にすることです。
たとえば:
- 登場人物の行動に驚いた
- 自分と似た経験があった
- 読んでいて悲しくなった、うれしくなった
そんな気持ちを、どうしてそう感じたのか、どんなふうに考えたのかを掘り下げていく。
それが、感想文の中心になります。
8割は、本文のことではなく自分自身について、もしくは、自分が考えていることを書くことが読書感想文のコツになります。
2. 書く前に「話す時間」をつくる
高学年になると、「自分で書きなさい」と言いたくなることもあります。
でも、書く前に「話す時間」を持つことで、子どもの考えが整理され、書きやすくなります。
おすすめの問いかけ:
- 「どんな本だった?」
- 「いちばん印象に残った場面はあった?」
- 「そのとき、どんな気持ちになった?」
- 「自分だったらどうすると思う?」
この「対話」が、感想文の土台になります。
話すことで、子どもは自分の気持ちに気づき、言葉にする準備が整います。
印象に残った場面、言葉を3つほど選び付箋を貼る作業をしておくと、文章の引用をする際に役立ちます。
3. 感想文の「型」を教えてあげる
高学年の子どもには、「自由に書いていいよ」よりも「型」を示す方が安心して書けます。
おすすめの構成:
- 本を選んだ理由
- 心に残った場面
- その場面で感じたこと・考えたこと
- 自分の経験とのつながり
- 読んで変わったこと・これからの自分
この型をもとに、話した内容をメモしておくと、文章にしやすくなります。
自分の経験を1つだけ書き、掘り下げていくこともできますが、2つ、3つ挙げることをお勧めします。経験を書くことで、文章の量も増えます。
4. 書き始めるまでの「小さなステップ」
感想文を書くために、いきなり「原稿用紙に向かう」のはハードルが高いもの。
おすすめのステップ:
- 話した内容を箇条書きにする
- それをもとに、短い文章にしてみる
- 原稿用紙に清書する(必要なら下書きも)
「まずは口で話す → 付箋を貼る→メモする →文章にする」
この流れが、子どもにとって自然で負担が少ない方法です。
文章を考えること、文字を書くことが苦手などもにとっては箇条書きも下書きをすることも面倒くさい作業と言えます。
ですが、本番の原稿用紙に書き終えたあとに親から書き方や内容を指摘され、書き直すことほど気持ちが辛くなることはありません。
一手間をかけて一緒に考えてほしいのです。
書くことが苦手な場合は、親がメモ書きしても良いと思います。
5. 書いたあとに「気持ちを受け止める」
感想文を書き終えたら、ぜひ読んであげてください。
そして、こんなふうに声をかけてみましょう:
- 「この気持ち、すごく伝わってきたよ」
- 「○○の場面で、こんなふうに考えたんだね」
- 「あなたらしい感想文だね」
評価ではなく、「気持ちを受け止める言葉」が、子どもにとって大きな励みになります。
6. よくある悩みとそのヒント
悩み アドバイス
あらすじばかりになる →「その場面で、どう感じた?」と聞いてみる
書き始められない→ 「話す→メモ→書く」のステップを試す
書きすぎてまとまらない →「伝えたいことを3つにしぼろう」と提案する
感情が浅くなる→ 「なぜそう感じたのか?」を一緒に考える
7. 感想文は「自分を知る時間」
読書感想文は、子どもが「自分の感じ方」「考え方」に気づく時間です。
それは、自己表現の第一歩であり、心の成長にもつながります。
親としてできることは、「書かせる」ことではなく、
「感じたことを言葉にする手助け」をすること。
それだけで、子どもは安心して、自分の言葉を見つけていきます。
おわりに:感想文は、親子の心をつなぐ贈りもの
読書感想文は、子どもが本を通して感じたことを、親に伝える「心の手紙」でもあります。
その手紙を、やさしく受け取ってあげてください。
そして、言葉にすることの楽しさ、伝えることの喜びを、親子で感じてみてください。
それは、きっと一生の宝物になります。